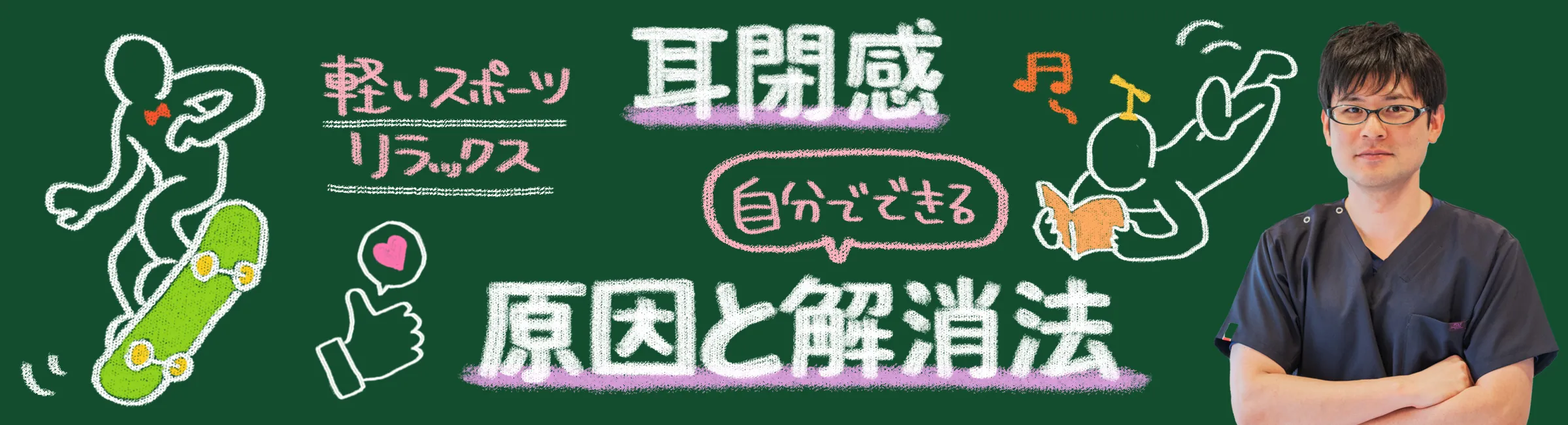
耳閉感は、多くの人が経験する不快な症状ですが、その正体や原因を理解している人は少ないかもしれません。突然の耳の圧迫感や聞こえにくさは、日常生活に影響を及ぼし、ストレスの原因となることもあります。この記事では、耳閉感のメカニズムやさまざまな原因、そしてその解消法について徹底的に解説します。耳閉感を軽減するための生活習慣やお手軽な対策もご紹介しますので、もし耳の違和感を感じているなら、ぜひ最後までお読みください。正しい知識を持ち、自分自身の健康を守る第一歩を踏み出しましょう。あなたの耳の悩みを解消するためのヒントがここにあります!
第1章 耳がふさがる…それ、耳閉感という症状です
「耳が詰まっているように感じる」
「こもったような音に聞こえる」
「水が入ったみたいで気持ち悪い」
このような感覚を、医学では**耳閉感(じへいかん)**と呼びます。
耳閉感は、耳そのものの異常だけでなく、脳や神経の働きとも関係があると考えられています。
第2章 耳閉感を引き起こす“原因”とは?
実は、耳閉感の原因はひとつではありません。耳の外側〜内側、さらには脳や心の状態まで、さまざまな要因が考えられます。
主な原因として知られているのは以下の通りです耳閉感の診断と治療:
● 耳の外側〜中耳の問題(伝音系)
- 耳垢のつまり(耳垢栓塞)
- 滲出性中耳炎
- 耳管狭窄症・耳管開放症(耳の内圧調整がうまくいかない状態)
● 内耳や神経の問題(感音系)
- 急性低音障害型感音難聴(ALHL)
- 突発性難聴
- メニエール病
- 上半規管裂隙症候群(SCDS)
● その他
- 顎関節症
- 不安・ストレスによる脳の過敏状態
- 自律神経の乱れ
とくに低音だけが聞こえにくくなるタイプの難聴や、耳管の開け閉めがうまくできない状態が、耳閉感を引き起こすことがわかっています。
第3章 医師による耳閉感の診察と治療とは?
耳鼻科では、まず耳閉感の「原因」を特定するために、次のような検査が行われます。
- 聴力検査(オージオグラム)
- 鼓膜や中耳の動きをみる検査(ティンパノメトリー)
- CTやMRIなどの画像検査
診断がついた場合は、以下のような治療が保険適用で行われます。
| 疾患名 | 主な治療法(保険診療) |
|---|---|
| 中耳炎、耳管狭窄症 | 鼓膜切開、通気、点鼻薬など |
| ALHL、突発性難聴 | ステロイド薬(内服・点滴) |
| 耳管開放症 | 塩水点鼻、体位の工夫など |
ただし、聴力に異常がなくても耳閉感がある場合や、検査では異常が見つからない場合、医療現場では「様子を見ましょう」となることが多くあります。
これは、保険診療では診断名がないと治療の選択肢が限られてしまうという背景があるためです。
第4章 それでも耳閉感がつらいあなたへ――私たちの治療法
私たちは、40年にわたり耳鼻科疾患に対する科学的な鍼灸治療を行ってきました。
その中で、多くの患者さんが「病院では異常なしと言われたのに、つらい」と感じていることに気づきました。
そこで私たちは、耳鼻科的な検査に加えて、次のような独自の評価と治療を取り入れています。
● サーモグラフィによる“温度分布”の観察
私たちは、耳のまわりや首・肩の体温の分布を「サーモグラフィ」という赤外線カメラでチェックします。
これにより、耳につながる血管の冷えや、自律神経のアンバランスを視覚的に確認できます。
● 耳に向かう“血流の変化”をリアルタイムで確認
耳の機能は、血流の状態と深く関係しています。
血のめぐりが悪くなっていると、耳が詰まったように感じることがあります。
私たちは、鍼を打ったあとに血流がどう変化するかを確認しながら、状態に応じて鍼の深さや位置を調整していきます。
● からだの感覚と脳の記憶をつなげて解きほぐす
耳閉感は、脳が過去の経験と照らし合わせて「耳に水が入ったときのような感覚」を再現していることがあります。
私たちはこの**「脳がつくる感覚」**にも注目し、体の感覚入力を整えることで、
脳の誤った知覚をやさしくリセットするお手伝いをしています。
第5章 診断がつかなくても、あなたのつらさは本物です
「異常はありません」「気にしないようにしましょう」
そんな言葉で済まされてしまう耳閉感。
でも、あなたが感じている不快感や不安は、決して気のせいではありません。
診断がつかなくても、治療の選択肢はあります。
そして、あなたに合った方法を一緒に探す人が必要です。
第6章 まずはお気軽に無料相談をご利用ください
私たちはこれまでに、東京・大阪・名古屋・新潟などからも耳閉感に悩む患者さんを受け入れてきました。
どんなに些細なことでも構いません。
あなたの耳閉感について、お話を聞かせてください。
📩 【無料相談フォームはこちら】鍼で治す耳鼻科の病気
あなたの“つらさ”を、私たちは“症状”としてきちんと受け止めます。
当院までのルートを詳しく見る
関東方面からお越しの場合
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
北陸・東海方面からお越しの場合
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で


