
ある日突然、片方の耳(まれに両耳)が聞こえにくくなる「突発性難聴」。
もし今、ご自身の「突発性難聴の症状」を確かめるためにこのページをご覧になっているなら、まずお伝えしたいことがあります。それは、突発性難聴は「耳の救急疾患」であり、一刻も早い対処が必要だということです。
しかし、お医者様の標準的な治療(ステロイド治療など)を受けても、残念ながらすべての方が回復するわけではありません。
「なぜ、自分の難聴は良くならないんだろう?」 「お医者様は忙しそうで、詳しい質問がしにくい…」
そんな不安や疑問を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事は、特に「お医者様の標準治療で良くならなかった方」や「ご自身の症状について、もっと深く知りたい」と願う方に向けて作成しています。
突発性難聴の基本的な初期症状のチェックリストから、なぜ専門家でも診断が難しいのか、そして標準治療で改善しにくい方に共通する「体の特徴」まで、詳しく解説します。
※出典 全日本病院出版会 ENTONI No.183 「突発性難聴update」
突発性難聴とは?
突発性難聴は、その名の通り「突然発症する」「原因が不明の」感音難聴です。
大切なのは「原因不明」という点です。 例えば、おたふく風邪(ムンプス)や内耳の腫瘍(聴神経腫瘍)などが原因で突然聞こえなくなっても、それは原因が特定できるため「突発性難聴」とは診断されません。
あくまで「検査をしても明らかな原因がわからない、突然の難聴」が、突発性難聴と呼ばれます。
突発性難聴のより詳しい原因や症状については、以下のページで網羅的に解説しています。
→ 突発性難聴とは?原因から治療法までを専門家が解説
突発性難聴の「初期症状チェックリスト」
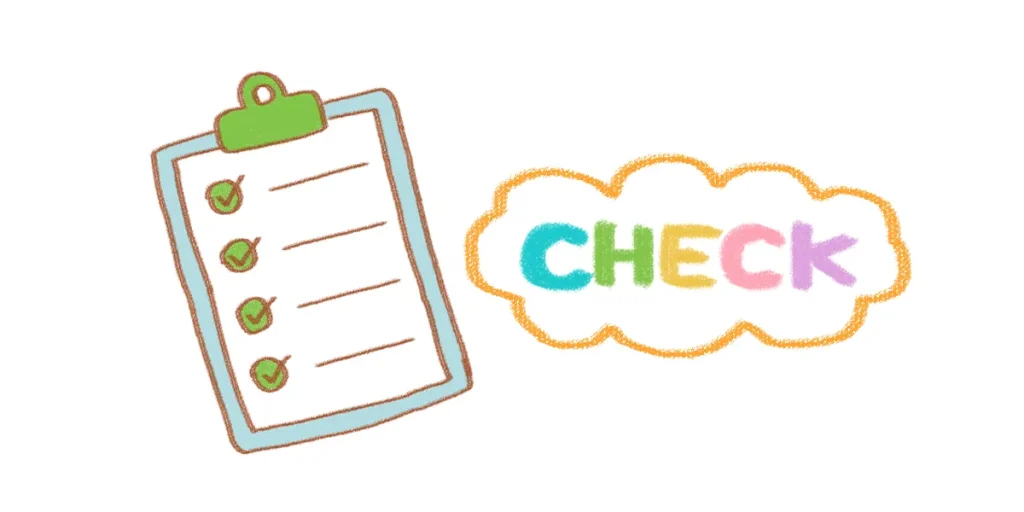
ご自身の症状が突発性難聴の典型的な症状と一致するか、チェックしてみましょう。
2012年に厚生労働省の研究班が示した診断基準(案)では、以下の症状が突発性難聴の目安とされています。
1. 難聴の発生(必須チェック)
□ 突然、耳が聞こえにくくなった
「文字どおり即時的」、「朝、目が覚めたら気づいた」 というように、いつ発症したかが明確なのが特徴です。
□ 72時間(3日間)以内に難聴が完成した
2012年の基準(案)で、発症の経過時間が具体的に示されました。
□ 特定の音(周波数)だけでなく、広い範囲で聞こえにくい
新しい基準(案)では「隣り合う3周波数で各30dB以上の難聴」という目安が示されました。
2. 伴うことのある症状(随伴症状)
難聴とほぼ同時に、以下の症状が現れることがあります。
「耳に水が入ったよう」「膜が張ったよう」と表現される方もいます。
□ 耳鳴り(キーン、ジーなど)がする
難聴の発生と前後して耳鳴りが生じることがあります。
□ めまい、ふらつき、吐き気がある
難聴と前後して、めまいや吐き気、嘔吐を伴うことがあります。
□ 耳が詰まった感じ(耳閉感)がする
「耳に水が入ったよう」「膜が張ったよう」と表現される方もいます。
専門家でも判断が難しい「突発性難聴と間違われやすい疾患」

突発性難聴の治療が難しい背景には、この「診断の難しさ」があります。
2012年に診断基準(案)が改訂され、「72時間以内に、隣り合う3周波数で30dB以上低下」という具体的な数字が示されました。 これにより診断の統一化が進む一方、かえって他の疾患との区別が難しくなるという新たな問題も生じています。
お医者様から「突発性難聴です」と診断されても、実際には以下の疾患である可能性、あるいは合併している可能性が隠れているのです。
1. 急性低音障害型感音難聴(ALHL)
- 特徴: 耳閉感や「ボー」という低い音の耳鳴りが特徴で、めまいは伴いません。
- 問題点: このALHLは、新しい突発性難聴の診断基準(3周波数で30dB以上)に当てはまってしまうことが非常に多いのです。
- なぜ重要か: ALHLは比較的予後が良く、内リンパ水腫(内耳のむくみ)が関係していると考えられています。突発性難聴とは異なる対応が必要な場合があります。
2. 外リンパ瘻(がいリンパろう)
- 特徴: 内耳と中耳の間にある膜が破れ、内耳のリンパ液が漏れ出す状態です。くしゃみ、鼻かみ、力み、頭部外傷などがきっかけで発症することがあります。
- 問題点: 最近、このリンパ液の漏れを検出する「CTP」というマーカー検査が注目されています。この検査で、明らかなきっかけがない(突発性難聴と診断された)患者さんの一部が陽性(=リンパ液漏れあり) と判定されることが分かってきました。
- なぜ重要か: 原因がリンパ液の漏れであれば、安静や手術的治療など、突発性難聴の治療(ステロイドなど)とは全く異なるアプローチが必要になります。
3. 心因性難聴(機能性難聴)
- 特徴: ストレスや心理的な問題が背景にあり、聴力検査では難聴を示すのに、内耳の機能自体は正常な状態です。
- 問題点: 特に小児に多いとされますが、成人でも見られます。
- なぜ重要か: DPOAE(歪成分耳音響放射)といった特殊な検査で内耳の機能を調べないと、難聴という「結果」だけを見て突発性難聴と診断されてしまうことがあります。
4. 聴神経腫瘍(ちょうしんけいしゅよう)
- 特徴: 聴こえの神経にできる良性の腫瘍です。
- 問題点: 腫瘍が大きくなる過程で、ある日突然、神経を圧迫して難聴を引き起こすことがあります。
- なぜ重要か: これはMRI検査でしか確認できません。突発性難聴と診断する前に、必ず除外すべき疾患です。
5. メニエール病
- 特徴: 激しい回転性のめまい発作を繰り返し、難聴や耳鳴りを伴う疾患です。
- 問題点: メニエール病の「初めての発作」が、めまいと難聴を伴う突発性難聴とそっくりで、区別が非常に困難なことがあります。
このように、「原因不明の突発性難聴」と診断された背景には、別の原因が隠れている可能性があるのです。
なぜ、お医者様の標準治療で良くならないのか?
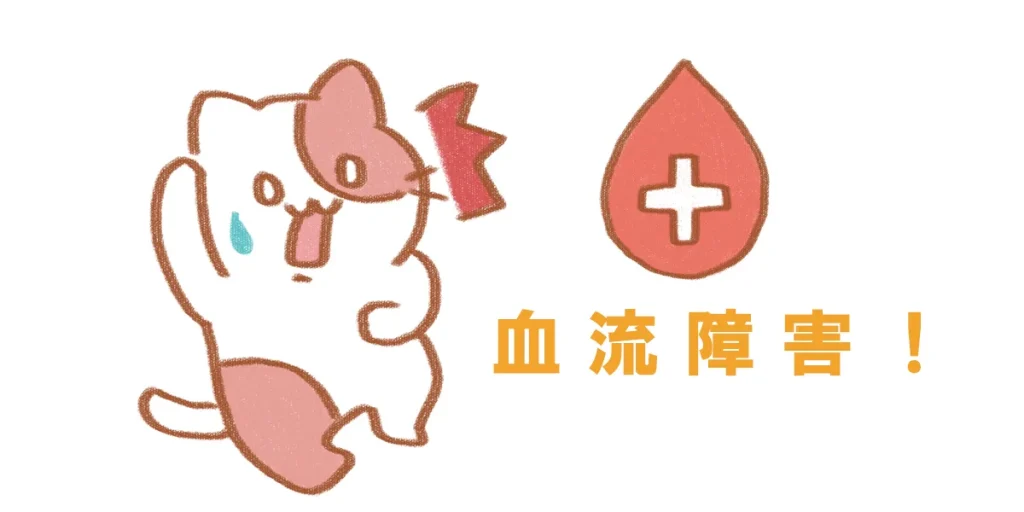
標準治療(ステロイドの点滴や内服)は、主に「内耳の炎症を抑える」ことを目的としています。
しかし、もしあなたの「聞こえにくさ」の根本原因が、上記のような「炎症」以外(リンパ漏れ、腫瘍、むくみ、または血流障害)だとしたら、ステロイド治療だけでは回復が難しいのは当然かもしれません。
突発性難聴の治療はEBM(根拠に基づく医療)の観点では、まだ「これ」という決定的な方法が確立されていないのが現状です。
標準治療で改善しにくい方の「体の特徴」
回復を妨げている「共通の身体的特徴(=根本原因)」というものがあり、多くの場合で「内耳への血流障害」が考えられます。
お医者様が処方するお薬は、全身を巡って患部に届きます。しかし、そもそも患部である内耳への「道(血管)」が塞がっていたり、細くなっていたりしたら、お薬の効果は半減してしまいます。
私たちが考える、回復を妨げる「血流障害」の主な原因は3つあります。
1.ふくらはぎの循環不全(梗塞体質) ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、全身に血液を戻すポンプの役割があります。この機能が低下していると、血流が滞りやすくなります。これは「エコノミークラス症候群」が起こりやすい状態、すなわち「梗塞体質(こうそくたいしつ)」とも言えます。 もし、ご家族(直系の近親者)に脳梗塞や心筋梗塞を発症した方がいる場合、ご自身もこの体質を受け継いでいる可能性があり、耳の症状が「全身の重大な疾患のサイン」である可能性も否定できません。
2.首や背骨の歪み(側弯) 首や背骨が歪んでいると、その中を通っている「椎骨動脈(ついこつどうみゃく)」という重要な血管が圧迫されることがあります。この血管は、耳や脳(平衡感覚の中枢)に血液を送る「命綱」です。ここが圧迫されれば、内耳は慢性的な栄養不足・酸欠状態に陥ります。
3.自律神経の乱れ(交感神経の過緊張) 過度なストレスや不規則な生活が続くと、自律神経のうち「交感神経(興奮・緊張モード)」が優位になり続けます。交感神経は血管を「収縮」させる働きがあるため、全身、特に末端(耳や手足)の血流が悪化します。
ステロイド治療が終わったら、どう考えるべきか
突発性難聴の治療は時間との勝負です。 一般的に、ステロイドの治療(1~2週間)が終わった時点で残っている症状(難聴や耳鳴り)は、その後、固定化しやすい(回復しにくくなる)傾向があります。
もし、お薬の治療で思うような結果が得られなかったとしても、それは「打つ手がない」ということではありません。 それは、「炎症を抑える」というアプローチでは改善しなかった、という「結果」がわかったに過ぎません。
大切なのは、その結果を受け止め、「なぜ改善しなかったのか?」という根本原因(血流障害など)に、できるだけ早くアプローチを切り替えることです。
諦める前にご相談ください(私たちの取り組み)
私たちは、お医者様で良くならなかった患者さんのための「次の選択肢」として、長野県須坂市で40年間、突発性難聴の専門治療に取り組んでいます。
これまでに14万人の突発性難聴の患者さんを診てきた経験上、初期症状の現れ方によって、回復のしやすさに傾向があることがわかっています。
- めまい・吐き気から始まった場合: 内耳の平衡感覚を司る場所まで深いダメージが及んでいる可能性があり、重症化しやすい傾向があります。
- 耳の詰まった感じ(耳閉感)・耳鳴りから始まった場合: ダメージが比較的浅いレベルで留まっていることが多く、回復しやすい傾向があります。
これは医学的な定説ではありませんが、現場での重要な所見です。特に「めまい」を伴う重症例であったとしても、諦める必要はありません。
1. 徹底した全身検査で「回復を妨げる原因」を特定します
なぜ良くならないのか? その「なぜ」を突き止めるために、聴力検査だけでなく、血流や体の歪みを可視化する検査を行います。
- 聴力検査・耳管機能検査・鼓膜の動きの検査(耳の基本的な状態把握)
- 医療用サーモグラフィ(自律神経の乱れによる体表温度・血流低下を可視化)
- 循環器用エコー(ふくらはぎなど第二の心臓の血流状態を評価)
- モアレトポグラフィ(首や背骨の歪みが血管を圧迫していないか可視化)

2. 根本原因にアプローチする専門治療
これらの精密検査に基づき、あなたの回復を妨げている根本原因(首の歪み、自律神経の乱れ、循環不全など)を特定し、内耳への血流を回復させるための専門治療を行います。
このアプローチにより、標準治療で改善しなかった患者さんの87.9%に、何らかの改善(聴力回復、耳鳴り軽減など)がみられています。
実際に改善された方の声
発症から1カ月でも聴力が回復
3. まずは、あなたの声をお聞かせください
「お医者様には相談しづらかった」 「説明が早くて、よく分からなかった」
私たちは、そのような患者さんの不安に寄り添うことを第一に考えています。 長野県須坂市の施設ですが、全国から多くの患者さんがご相談に来られます。
突発性難聴は、諦める必要のない疾患だと信じています。 まずはあなたの現在の症状、これまでの経緯、そして不安なお気持ちを、私たちに聞かせていただけませんか。
当院の「突発性難聴」に対する専門的なアプローチは、下記の専門ページで詳しく解説しています。
→ 突発性難聴 専門ページはこちら
「自分の症状でも改善の可能性があるか知りたい」「できるだけ早く相談したい」という方は、下記の無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。
→ 無料相談フォームはこちら
当院までのルートを詳しく見る
関東方面からお越しの場合
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
北陸・東海方面からお越しの場合
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で



