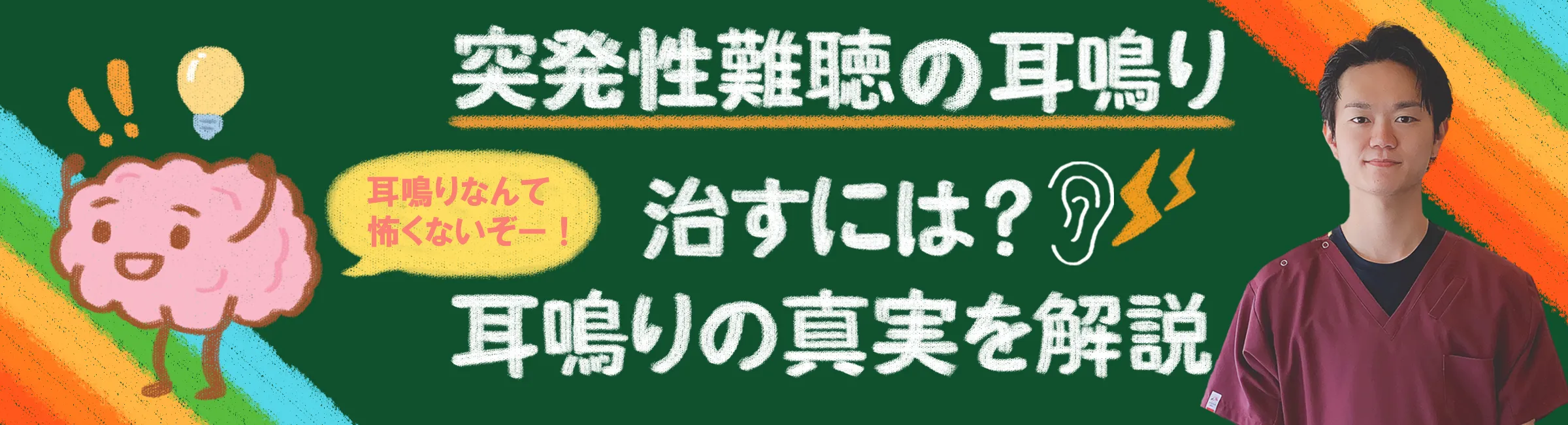
突発性難聴を発症し、治療を受けたものの「耳鳴り」だけが残ってしまい、お悩みではありませんか?
突発性難聴を発症された方の80〜90%が耳鳴りを伴うと報告されています 。耳鼻科でステロイド治療などを受けた後、幸い聴力が回復しても、耳鳴りだけが残ってしまうケースは少なくありません。
「キーンという高い音がずっと続いている」 「突発性難聴の耳鳴りはいつまで続くのだろうか」 「この耳鳴りはもう治らないのではないか」
このような不安を抱え、お医者様に相談したくても、日々の診察でお忙しそうで質問しづらかったり、不安な気持ちを十分に伝えられなかったりした経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、突発性難聴に伴う耳鳴りの「治しかた」について、その真実を詳しく解説します。
突発性難聴のより詳しい原因や症状については、以下のページで網羅的に解説しています。
→ 突発性難聴とは?原因から治療法までを専門家が解説
※出典 全日本病院出版会 ENTONI No.183 「突発性難聴update」
突発性難聴の耳鳴りはなぜ起こるのか?
耳鳴りが続くと、「耳の中で何かが鳴り続けている」と感じるかもしれませんが、実は耳鳴りの発生には「脳」が深く関係しています。
突発性難聴によって内耳の細胞(蝸牛)が障害を受けると、耳から脳へと伝わる音の信号が少なくなります 。すると、脳は「音が聞こえない」という事態に対応しようとして、感度を上げて過剰に興奮してしまいます 。この脳の過剰な興奮が、私たちが「耳鳴り」として感じている音の正体です。
さらに、この耳鳴りに対して私たちが「不安」や「ストレス」、「恐怖」を感じると、脳の苦痛を感じる部分が活発になり、耳鳴りをさらに強く意識させ、持続させてしまうという悪循環が起こることも分かっています 。
耳鳴りの音で治りやすさが分かる?
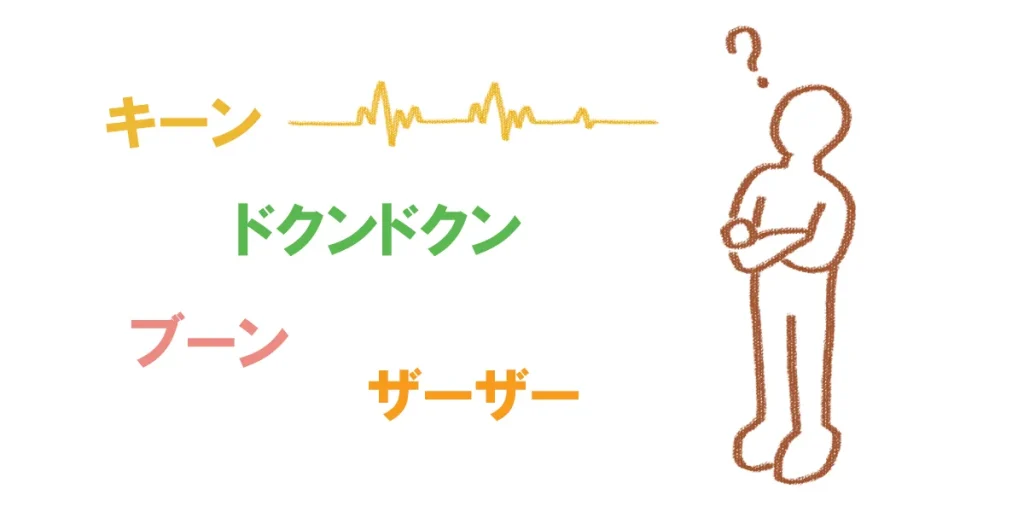
「突発性難聴になってから、高い音の耳鳴りがする」というご相談をよくいただきます。耳鳴りの音の種類によって、治りやすい・治りにくいといった傾向はあるのでしょうか?
医学的な研究では、耳鳴りの音質(「キーン」か「ボー」かなど)によって治りやすさが変わるという明確なデータは示されていません。
しかし、耳鳴りの音の種類には一定の傾向が見られることがあります。
- 改善傾向のサイン: 「ブーン」という低い音や、「ドクンドクン」「ザーザーザー」といった脈拍や血流を感じるような音の場合、その後の経過が良いことが多い印象です。
- 注意が必要なサイン: 「キーン」という高音の耳鳴りは、その後症状が悪化していく前兆のことがあります。また、「ザー」という砂嵐のような耳鳴りは、重症のケースで見られることが多いです。
これはあくまで一つの傾向であり、すべての方に当てはまるわけではありませんが、ご自身の状態を知るための一つの目安としてください。
突発性難聴の耳鳴り 治しかたの真実
耳鳴りの苦痛から解放されるためには、どうすれば良いのでしょうか。医学的にも重要とされている対処法は、主に「カウンセリング」と「音響療法」の2つです 。
ステップ1:カウンセリング(耳鳴りを正しく理解する)
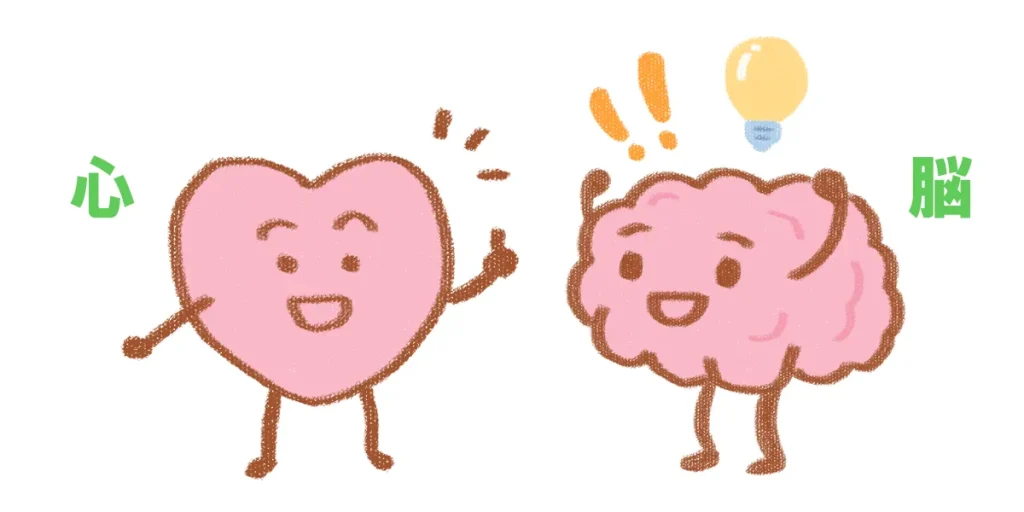
耳鳴り治療の第一歩は、ご自身の耳鳴りについて「正しく理解する」ことです 。
前述したように、耳鳴りは脳の興奮や不安が関係しています。そのため、医師から耳鳴りのメカニズムについて十分な説明(カウンセリング)を受け、「耳鳴りは危険なものではない」「脳の反応で起きている」と理解するだけで、不安が軽減されます 。
不安が減ると、脳の苦痛を感じる部分の興奮が静まり、耳鳴りへの意識が薄れていきます。その結果、耳鳴りの苦痛や大きさが時間とともに改善していく可能性が高いことが分かっています 。
「突発性難聴の耳鳴りはいつまで続くのか」というご不安もあるかと思いますが、適切な対処を行えば、半年から1年ほどで耳鳴りが(完全に消えなくても)気にならないレベルまで軽減することも多いのです 。
ステップ2:音響療法(特に「補聴器」の活用)
カウンセリングを受けても耳鳴りの苦痛が強く残る場合、次の選択肢として「音響療法」があります 。
音響療法には、ノイズを流す「サウンドジェネレータ(SG)」や「補聴器(HA)」を使う方法があります。
突発性難聴によって難聴が残っている方の場合、私たちは「補聴器」の使用を強くお勧めします。
ある研究では、サウンドジェネレータ(SG)は耳鳴りの「苦痛」を多少和らげるものの、「大きさ」自体にはあまり効果がありませんでした 。 一方、補聴器(HA)は、耳鳴りの「大きさ」と「苦痛」の両方に対して、著明な改善効果が認められたのです 。
これは、補聴器によって難聴の耳に再び周囲の音(環境音)がしっかりと入るようになると、脳の過剰な興奮が静まり、耳鳴りが軽減するためと考えられています 。
耳鳴り治療の注意点
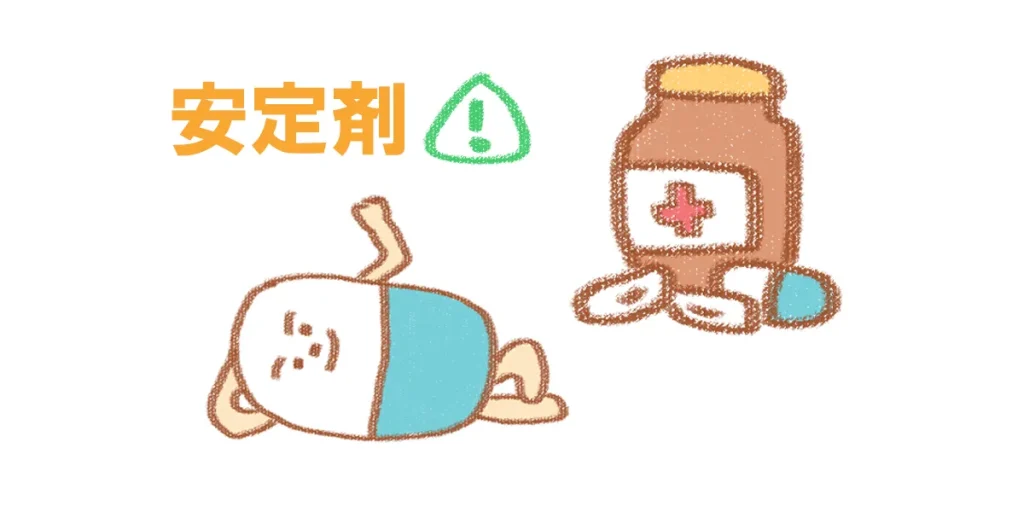
「色々試したが、突発性難聴の耳鳴りが治らない」と感じている方もいらっしゃるでしょう。
耳鳴りの治療には、実は「コツ」がいります。そのメカニズムを深く理解していないと、的外れな治療になってしまい、改善が難しくなることがあります。
例えば、耳鳴り自体を直接治すための保険適用のお薬は、現在のところ存在しません。そのため、安定剤が処方されることがありますが、これは一時的に不安を和らげるものであり、根本的な解決にはなりにくいと私たちは考えています。また、長期的な使用による副作用も気になるところです。
なぜ、あなたの耳鳴りは治らないのか?
耳鼻科の標準的な治療を受けても耳鳴りが改善しない場合、「耳」だけの問題ではなく、「体全体」に原因が隠れているかもしれません。
そうした方々には以下のような「お体の共通点(特徴)」が見られることが非常に多いです。
- 1.首や背骨のゆがみ(側弯) 首や背骨がゆがんでいると、耳や脳へ血液を送る重要な血管(椎骨動脈など)が圧迫され、血流が悪化していることがあります。
- 2.自律神経の乱れ(交感神経の優位) ストレスや緊張状態が続くと、自律神経のうち「交感神経」が優位に働きすぎます。これにより血管が収縮し、体全体の血流が悪くなり、体表温度が低下します。
- 3.ふくらはぎの温度低下(梗塞体質) 「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎの温度が低い方は、全身の血流が滞っているサインであり、いわゆる「梗塞体質」である可能性があります。
これらの「血流の悪化」が、ダメージを受けた内耳への酸素や栄養の供給を妨げ、回復を困難にしているのではないかと、私たちは考えています。
もし、ご家族や近親者に脳梗塞や心筋梗塞を発症した方がいらっしゃる場合、ご自身も梗塞体質を受け継いでいる可能性があります。その場合、その耳鳴りは、将来の重大な全身疾患につながるサインかもしれません。
お医者様の治療で良くならなかった方へ
耳鼻科での治療で改善が見られなかったとしても、決して諦めないでください。
私たち森上鍼灸整骨院では、長野県須坂市で40年間にわたって突発性難聴の専門治療に取り組み、これまでに110万人の患者さんと向き合い、そのうち突発性難聴の患者さんは14万人にのぼります。
また、当院では一般的な聴力検査、耳管機能検査、鼓膜の動きの検査に加え、以下のような専門的な検査機器を導入しています。
- 医療用サーモグラフィ: 体表温度を測定し、自律神経のバランスや血流の状態を可視化します。
- 循環器用エコー: 血管の状態や血流を詳細に観察します。
- モアレトポグラフィ: 骨格のゆがみ(側弯など)を正確に把握します。

これらの詳細な検査により、あなたの回復を妨げている「本当の原因」——それが血流の問題なのか、骨格のゆがみなのか、自律神経の乱れなのか——を突き止め、お一人おひとりに最適な治療プランをご提案します。
※来院される患者さんは、すべてお医者様の標準治療では改善が見られなかった方々で、当院の専門治療を受けられた方のうち、87.9%の方に何らかの改善が見られています(※)。
(※)聴力回復、耳鳴り・めまいの軽減、QOL(生活の質)の向上などを含む
実際に改善された方の声
諦めなくてよかった
「もう治らない」と一人で悩み、不安を抱え続けるのは、耳鳴りを悪化させてしまう可能性もあります 。お医者様には相談しにくいこと、今抱えているお悩みや不安を、まずは私たちにお聞かせください。
治療には前向きな姿勢と継続的な取り組みが必要となりますが、私たちはあなたのそのお気持ちに寄り添い、全力でサポートすることをお約束します。
当院の「突発性難聴」に対する専門的なアプローチは、下記の専門ページで詳しく解説しています。
→ 突発性難聴 専門ページはこちら
「自分の症状でも改善の可能性があるか知りたい」「できるだけ早く相談したい」という方は、下記の無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。
→ 無料相談フォームはこちら
当院までのルートを詳しく見る
関東方面からお越しの場合
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
北陸・東海方面からお越しの場合
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で
バスで
電車で



